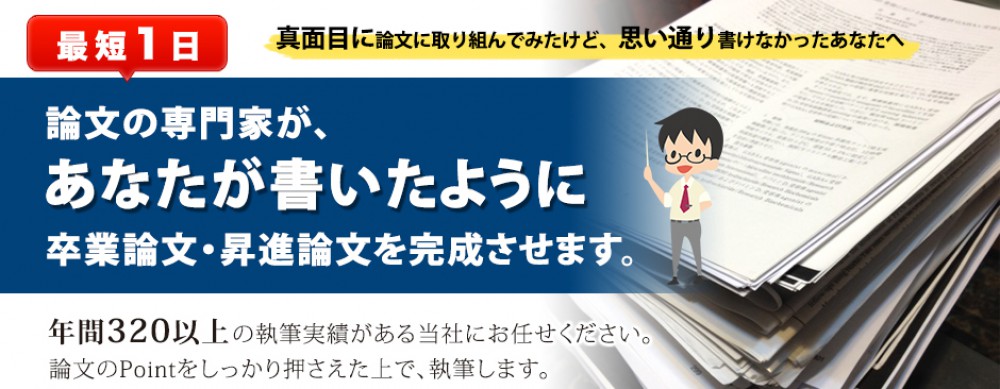先日依頼いただいた案件が無事完了しました。依頼主様からのお礼を報告します。お役に立てて幸いです。
☆依頼主様からのお礼
この度は、大変お世話になりありがとうございます。
原稿につきまして、2度手直しいただくなど、大変有難く勉強になりました。
この原稿を基に、小生にて、具体的なインパクト数値などを盛り込み、
加除筆、文切調にいたしました。
※最終稿をご参考までにお送りさせていただきます。
本件にて校了、納品完了です。
メール拝受のご返信と御礼まで。
☆☆解説
昇進試験の論文代行の場合、どうしても社内の特別な事情があったり、社内の方でないとわからない情報もあります。当社では経験豊富な執筆者が代行しますが、それでも原稿がイメージと違う場合もあります。そういった場合、納品後すぐにご連絡をいただければ、具体的な部分をヒアリングさせていただき、可能な範囲で原稿の修正にとりかかります。
上記お礼にもあるように、具体的な数値などは依頼主様本人に加筆いただくようお願いしております。また、いただいた情報をもとに執筆しているので、伝え漏れがあったり、認識の齟齬もありえます。そういった部分も問題を少しでも解決できるように、このような対応を取らせていただいております。
依頼主様の声で多いのは、当社からの原稿を読んで「頭の中がクリアになった」という感想です。専門の執筆者が頭の中で漠然と思い浮かべていることを言語化することで、言いたかったことが見えてきます。
昇進論文を一人で作成する場合、独りよがりになってしまったり、視点が漏れたりすることがあります。これまでの実績や業績のある方でも、採点するのが外部の業者であったり、ご自身の業務内容に精通されていない方の場合だったりすると、なかなか評価を得られません。
書ける屋に論文代行を依頼されたり、対面打ち合わせされた方の多くはご存知ですが、「どなたが昇進論文を採点すると思われますか?」という質問があります。上記のように全くの第三者の場合、業務の概略を説明します。逆に、ご自身の業務内容に詳しい方が採点に当たる場合、現状の課題内容を掘り下げて論じるといった対応をしております。
以上です。
関連記事
昇進レポートがまとまらないときはどうする?